
投稿日:2024/10/03
更新日: 2024/10/03
すぐに使える!ロードバイクの輪行テクニック
ときどき、駅のホームや電車内で大きな袋を担いでいる人を見かけませんか?もしかしたら、その人はロードバイクを抱えた輪行中のサイクリストかもしれません。サイクリストにとって、輪行は習得しておきたいスキルの1つです。
輪行をすることで、自走では行けない土地でのサイクリングを楽しんだり、万が一トラブルが発生して走れない状態になってしまった際の脱出ツールとして活用することができます。遠方までサイクリングを楽しんで、帰路は電車で楽々帰宅…といったことも可能ですね。
ですが輪行ってどうやったらいいの?と疑問を持つ人も多いと思います。特にビギナーサイクリストの方は、まず輪行に必要なアクセサリー集めからスタートしなければなりません。今回は、これから初めて輪行にチャレンジするサイクリストに向けて、ユーザーの多い「リムブレーキロードバイクの輪行ポイント」を紹介していきます。
輪行をマスターしてサイクリングの幅をさらに広げていきましょう!
輪行とは

輪行とは「自転車を分解して専用の袋に入れ、電車などの公共交通機関で運ぶこと」を指します。現在の日本では、電車・バス・飛行機・フェリー等の公共交通機関で輪行をすることが可能です。
【輪行のメリット】

- 自宅から離れた旅先でも自転車を楽しめる
- 遠方から公共交通機関で楽に帰宅できる
- 自走できなくなるメカトラが起きても輪行帰宅が可能になる
- ガソリン・高速代よりも電車賃の方が安く済む場合がある(節約できる)
上記で挙げたように、輪行をマスターすることでより一層自転車を楽しむことができます。サイクリストとしてもレベルアップしたような気持ちになれますね。
ルール・輪行の種類についてはこちら:RouteShare | RouteShareで県外へ輪行サイクリングに出かけよう! (route-share.net)
輪行に必要なもの
それでは、輪行をするにあたって必要なアクセサリーをチェックしていきましょう。
※写真は著者のロードバイク(リムブレーキ・エンド幅130㎜・シマノ電動シフト式)用に実際に所持しているものとなります。実際に自分の自転車の規格を確認してから揃えることをおすすめします。
必須アイテム
- 輪行袋
- エンド金具
- 車輪をまとめるバンド(最低三本)
- 肩紐
【輪行袋】

縦型、横型とありますがどちらでも大丈夫です。縦型は縦長に収納できるので省スペースできるメリットがりますが、ディレーラーハンガー保護のためにエンド金具が必須となります。横型はエンド金具なしでも輪行可能な反面、横広になるので横幅が広いスペースの確保が必要です。
JRなどの鉄道では、基本的に自転車を完全に覆える袋に入れなくてはなりません。車輪がむき出しだったり、自転車の一部がはみ出るような袋では乗車を断られてしまいますので、きちんと専用の輪行袋を用意して、適当な袋に入れることがないようにしましょう。
飛行機輪行の場合は、より堅牢な箱型の輪行袋(輪行箱)がおすすめです。国内線ではあまり体験したことがありませんが、航空会社によっては投げられたり、他の乗客の荷物に押しつぶされて壊れてしまう恐れがあります。強度が高い外箱を用意して、緩衝材をしっかり巻き、万が一のトラブルに備えたいですね。
【エンド金具】

エンド金具とは、車輪を外したロードバイクのエンドに代わりに嵌めておく保護金具です。フロント用、リア用があり、それぞれ前輪と後輪が嵌っていた場所に取り付けをします。縦型輪行袋使用の際は必需品ですが、この部分の選び方には注意があります。
まずは自分のロードバイクの車輪固定方法・エンド幅を必ずチェックしましょう。
| 【車輪固定方法】 | 【エンド幅】 |
| ①クイックリリース式 | ①130mm(リムブレーキロードバイクの主流) |
| ②スルーアクスル式 | ②135㎜(クロスバイクの主流) |
| ③142㎜(ディスクロードバイクの主流) |
上記のように、大きく分けて車輪の固定方法は2種類、エンド幅は3種類あります。厳密には独自規格やブースト規格を含めるとさらに種類があるのですが、今回は主流の規格のみ記載しました。
画像はクイックリリース式×エンド幅130㎜用のエンド金具となります。他の組み合わせの規格のものとは互換性がありません。つまり、自分の自転車の規格に合った金具を用意しないと使えなくなってしまうので注意してください。悩んだら自転車屋さんに相談を。
【車輪をまとめるバンド(最低三本)】

分解した自転車はそのままではバラバラの状態なため、まとめて固定しておくバンドが必要です。車輪を時計に見立てて、2時、6時、10時あたりを3点固定すると安定感が増します。マジックテープのベルトやゴムバンドなどがありますが、使いやすければなんでもOKです。
著者はゴムバンドタイプを使用し、伸びてきたら買い換えています。(3年に一回くらいの買い替えです)
【肩紐】

ロードバイクを収納した輪行袋を担ぐために、肩紐を結び付けておかなくてはなりません。なるべく太めの方が肩への負担が軽減します。それでも肩に食い込んで痛い場合は、ショルダーバッグ用の肩当を仕込んでおく小技がありますよ。
ほとんどの輪行袋では付属していますが、著者が購入した輪行袋は付属していなかったので別で購入しました。
あると便利なオプションアイテム
- スプロケットカバー
- チェーンガード・チェーンフック
- ディスクローターカバー※ディスクブレーキの場合
- ブレーキパッドスペーサー※油圧ディスクブレーキの場合
- ショルダーパッド
【スプロケットカバー】
チェーンオイルが付着しているスプロケットをむき出しで入れると、輪行袋が汚れてしまう恐れがあります。輪行前にクリーニングしたから大丈夫!と思っていても、サイクリング帰りに輪行しようとしたら汚れでギトギトになっている場合も…。そんな時は、スプロケットカバーがあると輪行袋の内側やフレームを汚さずにパッキングできますよ。
【チェーンガード・チェーンフック】

スプロケットカバーと同じく、チェーンオイルの汚れや擦れからフレームを保護するために使用します。ない場合はウエスや緩衝材をチェーンステーに巻いてもOKです。
【ディスクローターカバー】※ディスクブレーキの場合

ディスクブレーキの場合は、ホイールのディスクローターにカバーをかけておくと安心です。ディスクローターが衝撃で曲がるのを防いでくれるほか、チェーンオイルが輪行中にうっかりローターに付着してしまい音鳴りが発生してしまうトラブルも防止できます。
音鳴りは非常に厄介で、ディスクローターからさらにパッドに油分が移ってしまうとすべて交換になって高額修理に発展する可能性があります。輪行時はチェーンを触った手でディスクローターに触れないように注意してください。
【ブレーキパッドスペーサー】※油圧ディスクブレーキの場合
油圧ディスクブレーキは、ホイールを外した状態でブレーキレバーを握ってしまうと、オイルの圧でピストンが飛び出してしまいます。そうなると、パッド同士の隙間が狭くなり、車輪が嵌められなくなったり、元に戻せてもシャリシャリと擦れるような音鳴りが発生します。
対策として、車輪を外したらブレーキキャリパーの隙間にブレーキパッドスペーサーを挟めておきましょう。もしもブレーキレバーを握ってしまっても、スペーサーがいることでピストンが出きってしまうのをh瀬げます。輪行時に抜けてしまわないようにゴムやバンドで固定しておくと尚良しです。
【ショルダーパッド】

輪行袋は肩紐を用いて袋を浮かせながら移動しますが、少自転車分の重さが肩にかかります。この時肩紐が細くなったり捻れるとものすごい圧力が肩にかかります。移動中も痛く辛く、帰って風呂に入った時に鏡を見たら肩が真っ赤!!となることもあります。
筆者も輪行の時のこの肩の痛みは本当に嫌で、長いホームの移動など自転車を捨てたくなります。その時、痛みを軽減するためにショルダーパッドに肩紐を挟んで、肩に乗っけるといいです。もし今持っていない場合は畳んだタオルなどで代用できます。
リムブレーキロードバイクの輪行手順

輪行に必要道具が揃ったら、次は早速実践編です。駅から電車に乗せて輪行すると仮定して、ロードバイクの分解から縦型輪行袋に詰める流れを説明していきます。※到着後の組み立ては逆手順です。
分解からパッキングまでの流れ
- 広めの作業スペースで自転車を逆さにする
- アウター×トップに入れてホイールを外す
- エンド金具を取りつける
- リアの変速を最大ロー側に入れる
- ホイールとフレームをバンドで固定する
- 肩紐を取りつけて、輪行袋に入れる(パッキング)
各手順のポイント
1.広めの作業スペースで自転車を逆さにする
駅に到着したら、最初に自転車を分解してパッキングする作業スペースを確保します。改札口に行きやすく、人の邪魔にならない広めの場所がマストです。組み立て中に自転車が倒れないように、壁があるとさらに良いでしょう。
場所を見つけたら、自転車から前後のライト・サイクルコンピューター・ボトルなどのアクセサリーをすべて外します。この時に外したアクセサリーをまとめておける袋があると便利です。特にハンドル周りは自転車をひっくり返すときに邪魔になってしまうので全部外します。

次に自転車を逆さまにして自立させます。外せないマウントなどの関係で自立が難しい場合は壁を利用してください。

2.アウター×トップに入れてホイールを外す

車輪を外しやすくするために、フロントをアウター・リアをトップに変速します。本来はフロントをインナーに落とした方がチェーンの張りが緩くなって一番外しやすくなるのですが、アウターチェーンリングのギザギザで輪行袋が傷つかないように、保護のためにフロントはアウターに入れます。

リアをトップに入れてチェーンが緩んだら、クイックレバーを解除して前後輪を抜きます。この時、クイックレバーのバネやキャップを紛失しないように気を付けましょう。

3.エンド金具を取り付ける
前後輪が外れたら、今までホイールが入っていた部分にエンド金具を取り付けます。エンド金具を使用することで、フレーム・リアディレーラー・ディレーラーハンガーを保護する役割があります。取り付けの角度は。だいだいチェーンステーと同一ライン上くらいが目安。

※今回はリアエンド金具のみ使用しますが、フロントフォーク側も保護したい方はフロント用を併用してください。
ここでワンポイントですが、できる方はチェーンのたるみをとるためにチェーンフッカーにチェーンをひっかけておくとチェーンステーの擦り傷防止になります。

4.リアの変速を最大ロー側に入れる

先ほど車輪を外す際にトップに入れていたリア変速を、今度は最大ロー側まで動かします。こうすることによって、リアディレーラーが内側に入り、外からの衝撃で壊れにくく、ディレーラーハンガーが曲がりにくくなります。
5.ホイールとフレームをバンドで固定する
エンド側の下準備が済んだら、ホイールとフレームをバンドで固定します。クランクを水平の状態にして、両側からホイールでフレームをサンドイッチのように挟みます。この時、ペダルがホイールに乗っかるようにしてあげるとズレにくくなります。

バンドで固定する位置は最低3か所です。ホイールを時計だとして、2時、6時、10時くらいの位置にバンドを通して、ホイールとホイールでフレームを挟み込んだ状態のまま固定します。

最後に、ハンドルを曲げてスポークの隙間に入れ込んだら完了です。ハンドルが動かないように固定すると運びやすくなるので、バンドを1本追加で持ち歩いています。

袋に入れる前に、サドルとエンド金具の2点で自立するように立てます。この際にエンド金具の位置が地面と垂直になるように微調整します。

6.肩紐を取り付けて輪行袋に入れる(パッキング)
肩紐はBB下とステムの2点で固定します。

持ち運びやすい長さは身長によって変わってくるので、ベストな長さをマーキングしておくと後々楽になります。肩紐を付けたら、輪行袋で完全に覆います。

パッキングを終えたら、あとは公共交通機関に乗り込むだけ。ですが、家に着くまでが遠足なのと同じように目的地に着くまでが輪行です。移動中の注意点は次項にまとめたので参考にしてください。
輪行時の注意点
- 輪行袋は丁寧に扱う
- 他の乗客の邪魔にならないようにする
- 自転車は完全に輪行袋で包むこと
- 各公共交通機関のルールに従うこと
自分も乗客の一人なので、場所は譲り合って使用するのがセオリーです。優先席や車いすスペースを占有して本来使いたい人の邪魔になったりしないようにしましょう。サイクリスト全体の印象が悪くなり、その交通機関で輪行が禁止になってしまうかもしれません。
また、JRは特に厳しく「袋からはみ出ていないか」をチェックされます。自転車を輪行袋に入れる際は、完全に覆って包んでください。袋からはみ出たハンドル・サドルが人にぶつかってほかの乗客がけがをしたら…トラブルの原因になってしまいます。
輪行の際は公共交通機関で定められた持ち込みルールを必ず順守し、お互いが気持ちよく利用できるように心がけることが大切ですね。
まとめ
以上が、リムブレーキユーザー向けの縦型輪行術の紹介でした。実際に輪行用のアクセサリーが揃ったら、一度自宅でパッキング~組み立てまでの一連の流れを練習してみることをおすすめします。自分の自転車はこうすると楽!というコツを掴んでおけば、いざ実践となっても緊張せずスムーズにできるはずです。
今までのサイクリングに輪行を取り入れて、更に自転車ライフを充実させていきましょう!どこに出かけようか悩んだら、ぜひRoute Shareを参考にしてくださいね。
公式SNSで情報を発信中
RouteShareの使い方、旅行情報・テクニックなど楽しく旅行ができるノウハウを紹介しています。ぜひフォローしてください。
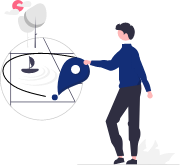
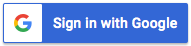
Googleアカウント、メールアドレスで無料ですぐに始められます。
登録後にStravaを連携することでアクティビティからすぐに
ルートをインポートすることも可能です。

