
投稿日:2024/10/30
更新日: 2024/10/30
サイクリスト必須スキル!ロードバイクのパンク修理講座
みなさんは、今まで自転車のタイヤがパンクしてしまった経験がありますか?近場であれば家族に迎えに来てもらって、そのまま自転車屋で修理してもらうことができますが、長距離サイクリングの場合は自力で修理をして帰宅しなければなりません。そんな時に必要なのが「パンク修理スキル」です。
今回は、サイクリング・ツーリング中で一番多いトラブルである「パンク」への対処法を紹介していきます。安心して長い距離を走れるように、パンク修理のスキルを取得しましょう!
パンクってどんな状態?

パンクとは、チューブに穴が開いてしまい空気を保持できなくなってしまった状態です。空気の入っていないぺちゃんこに潰れた風船と同じイメージで、そのままではクッション性がないので自転車を走らせることができません。出先でこうなってしまうと、そこから帰宅する手段がなくなってしまうため、サイクリストにとってパンク修理は必須スキルといえるのです。
パンクの主な原因としては、以下の3つが挙げられます。
- 釘や鋭利な破片などが突き刺さったパンク
- 空気圧不足によるリム打ちパンク
- タイヤ・チューブの劣化・摩耗によるパンク
突き刺さりパンクは運もありますが、リム打ちは空気圧管理をしっかりとすれば回避できますし、タイヤ・チューブの摩耗は交換時期を守ればリスクを減らせます。これから紹介するパンク修理の方法をマスターすると同時に、パンクしないための機材管理を頭に入れておくことが大切です。
※スポーツサイクルの場合、空気圧管理はできれば乗るたびにチェックするのがおすすめです。タイヤ・チューブはゴム製品のため、すり減っていなくとも2年ほど経過すると水分が抜けて硬くなってしまうので様子を見て交換してあげましょう。
タイヤの仕組みを覚えよう
パンク修理の前に、自分の使っているタイヤの特性・仕組みをチェックしておきましょう。今回の記事では、クリンチャータイヤのパンク修理について掘り下げていきます。
クリンチャータイヤ
- タイヤの中にチューブを入れて使用する
- 一般車(ママチャリや子供車)にも採用されている一番メジャーな種類
- 低価格~高価格帯まで幅広いラインナップがある
- パッチを貼って応急処置的なパンク修理が可能
- 取り付け・交換が容易に行える
- 修理の際にほとんどの自転車屋で入手できる
- 悩んだらクリンチャーを選択しておけば間違いない
チューブレスタイヤ
- タイヤの中にシーラントを呼ばれる液体を入れて使用する
- 近年市場拡大し、ユーザーが増加している
- クリンチャーよりも空気圧を低く設定できるので、乗り心地とグリップがいい
- 中価格帯~高価格帯
- パッチによる修理は不可能
- 取り付けに力を要するものが多い
- タイヤとシーラントの相性に左右される
チューブラータイヤ
- チューブとタイヤが縫い付けられて一体化したものを、リムセメントでホイールに貼り付けて使用する
- しなやかで軽い乗り心地
- 欧州プロがレースに使用しているが、一般サイクリストで使用者は減っている
- タイヤチューブが一体化しているのでパンク修理不可
- 高価格帯(クリンチャーの2倍くらいの価格)
- 取り付けに力・技術を要するものが多い
- 年々ラインナップが減少してきている
また、クリンチャータイヤの中に入れるチューブですが、今回はゴム製のブチルチューブを前提として開設を進めていきます。乗り心地がしなやかになる「ラテックスチューブ」や、軽量かつ安価で話題の「TPUチューブ」では紙やすりと糊を使ったパッチ修理ができませんのでご注意ください。
パンク修理キットの中身って?

では出先でもしパンクしたら?基本的にはチューブ交換となりますが、持って行った替えのチューブすらもパンクしてしまった時はパッチを貼って応急処置が必要になります(方法は後述します)
※なぜ基本的にチューブ交換になるかというと、スポーツサイクルは一般車よりも空気圧が高圧になるため、パッチが剝がれやすくその場しのぎ程度になってしまう可能性が高いです。そのため、新品のチューブに交換することが推奨されます。
もしもの時すぐに作業できるように、サドルバッグやツールボトルに「パンク修理キット」を入れて携帯しましょう。中に入れるべきアイテムは以下を参考にしてください 。
パンク修理キットの中身

- パッチ
- 替えチューブ
- タイヤレバー(最低2本。3本あると楽)
- ミニポンプ
- Co2ボンベ・インフレーター(Co2を充填する道具)※あれば楽
- 電動空気入れ※あれば楽
- 古タイヤの切れ端・タイヤブートなど※サイドカット修理用
スルーアクスルの方は、車輪脱着用に対応した工具が必要になりますが、共通して用意しておきたいパンク修理キットの中身は上記の通りです。空気を入れるためにミニポンプは必須です。ただし何十回とポンピングしなければならないので、労力を軽減させるためにCo2ボンベ・電動空気入れを持ち歩くのもおすすめです。
ミニポンプは何度でも使えますが、Co2ボンベは使い切りで1個当たり¥300~¥500ほどかかります。電動空気入れはいざというとき充電切れだと意味がなくなってしまうので、出発前にはしっかり充電をしておきましょう。
※スルーアクスル…ディスクブレーキ車で主流となっている車輪の固定法で、クイックリリースレバーとは異なり、六角レンチを使用して車輪を固定します。
パンク修理①【チューブ交換編】
チューブ交換の流れ
- 自転車からホイールを外す
- 異物が突き刺さっていないかをチェックする
- タイヤのビードをリムの中に落とす
- タイヤレバーでタイヤを外す
- 中のチューブを取り出す
- タイヤ内に異物が残留していないかチェックする
- 新しいチューブに軽く空気を入れる
- タイヤをはめる
- 空気を入れる
- ホイールを自転車に戻す
修理のポイント
【自転車からホイールを外す】
ギアをフロントインナー×リアトップに入れてチェーンテンションを緩めてホイールを外します。
【異物が突き刺さっていないかをチェックする】

ホイールを外したら、目視でタイヤを確認します。刺さっている異物があればこの時点で除去し、他に残っていないか手で触って一周確認してください。この時に異物が残ったままだと、新しいチューブにもまた穴が開いてしまいます。
【タイヤのビードをリムの中に落とす】

タイヤのフチのフックのようになっている部分を「ビード」と呼び、ビードがホイールに引っかかることで固定されています。今回はタイヤを外したいので、ビードを指で押してリムの中に落としていきます。
ここでポイント!車のハンドルを握るようなイメージでタイヤを持ち、手は時計でいうと10時10分の位置にすると力を入れやすくなります。両手の親指を使ってググっとリムの内側に落としてください。

上から見てリムの内側が見えていればOKです。これを両面作業します。
【タイヤレバーでタイヤを外す】

タイヤレバーを使ってタイヤを外します。用意するレバーは2~3本。まず1本目は、タイヤレバーのフック状になっている方でタイヤを持ち上げ、スポークに引っ掛けて浮かせておきます。2本目以降は、引っかけてはタイヤを外し、引っかけてはタイヤを外し…といった作業を繰り返しながら、横へ横へとタイヤを外して行きます。

ホイールの半分くらいまでタイヤレバーを差し込んでいくと、あとは手でタイヤを外せるくらい緩くなるのでタイヤレバーは不要です。

この時に、タイヤレバーをスライドして外してしまいたいところですが、タイヤ内部やチューブが傷んでしまうので注意してください。
タイヤをホイールから外すのは片側のみでOKです。

【中のチューブを取り出す】

これで片側のタイヤが外れ、チューブが見えてくるので手で優しくチューブを取り出します。バルブの部分は外れにくいため、タイヤを上に持ち上げると楽です。

【タイヤ内に異物が残留していないかチェックする】
チューブを外したらタイヤの裏側をぐるっと一周手で触り、最初に目視チェックしたようにタイヤ内にパンクの原因の異物が残留していないか確認します。

この時に、タイヤのサイドに大きく穴が開いている現象を「サイドカット」と呼びます。このまま新しいチューブを入れても、サイドカットの穴からチューブが出ようとして再度パンクしてしまうので、タイヤごと交換が必要になります。
※出先だとタイヤ交換まではできないので、サイドカットの場合は内側から紙や古タイヤの切れ端などを当てて応急処置をしましょう。タイヤブートと呼ばれる専用品も販売されています。これらを当てがってひとまず帰宅できる状態にし、後ほどタイヤを交換してください。
【新しいチューブに軽く空気を入れる】

タイヤ内に異物が残っていないことを確認したら、新しいチューブを入れます。ある程度チューブに厚みがないと入れにくいので、軽く空気を入れて膨らませてください。入れすぎはNGです。
最初にバルブホールにバルブ口を入れ、そのあと残りの部分をタイヤに入れ込みます。

【タイヤをはめる】

手順3で落としたビードを、今度は逆にはめていきます。両手の親指を使ってタイヤをはめていきますが、チューブを挟み込んだままタイヤを戻してしまうと、実際に指定空気圧まで空気を入れた際にバーストしてしまいます。必ずチューブが挟み込まれていないのを最後に確認します。
※こちらの画像はチューブを挟み込んでしまっているNG例。

【空気を入れる】
タイヤを一周はめて、チューブの挟み込みがないかチェックしたら空気を入れます。最後に手で軸を持って回転させ、ビードがきちんとはまっていればきれいにタイヤのフチのラインが出ます。
【ホイールを自転車に戻す】
インナートップの状態のままでホイールを戻します。最後にブレーキの動作確認(後輪を外した場合は変速も動作確認を)を行って完了です!
パンク修理②【パッチによる応急処置編】

パッチ貼りの流れ
※チューブ交換手順の6と7の間にパッチ貼りが入ります。
- 軽く空気を入れて穴の位置を探す
- 穴の周辺を紙やすりで削る
- パッチを貼る
- もう一度空気を入れて、抜けないかチェックする
修理のポイント
【軽く空気を入れて穴の位置を探す】

空気が抜けていく穴を探すため、ミニポンプ等を使ってある程度空気を入れます。耳を近づけてシューと音が鳴る箇所や、指で触って空気が出ていく感触がある箇所を見つけましょう。
【パンク穴を見つけるコツ】
空気の音だけでは穴の個所が分かりにくことがあるので、家やホテルなどの水が使える環境の場合、水調べをすると穴の位置を確実にチェックできます。桶などに水を溜めて、軽く空気を入れたチューブを水に通すと、パンク穴から小さな泡が出てきます。穴を見つけたら、見失わないように赤油性ペンなどで印をつけておきましょう。
【穴の周辺を紙やすりで削る】

穴の位置が判明したら、パッチの密着度を上げるために周辺を紙やすりで削って凹凸にします。パッチを購入するとついてくる紙やすりで大丈夫です。削ると穴の位置が分かりにくくなるので、見失わないように注意してください。
【パッチを貼る】

紙やすりで凹凸を作った箇所にパッチを貼りつけて穴を塞ぎます。シールタイプのパッチであればそのまま貼り付けますが、糊が別でチューブに入っているタイプはしっかりと糊の膜を作り、十分乾燥させてからパッチを乗せて圧着します。
油分が付着しているとパッチがつきにくいので、削った面を手で触って皮脂をつけたり、チェーンオイルなどがうっかり付いてしまわないように気を付けましょう。
【もう一度空気を入れて、抜けないかチェックする】
最後に再度空気を入れて、パッチの剥がれはないか・空気の漏れはないかを確認してください。問題がなければ、チューブ交換の手順でチューブを戻します。
万が一、入れたばかりの新品チューブがパンクしてしまった時には、この方法でパッチを貼って応急処置を施しましょう。あくまでもその場しのぎの作業ですので、帰宅したらチューブ交換するのをお忘れなく。
チューブレス・チューブラーの場合
チューブレスタイヤがパンクしたら
チューブレスタイヤは中にシーラントを入れて運用するので、ある程度の穴であればシーラントが自動的に穴を修復してくれます。ですが大きな穴が開くと、パンクを防ぎきれずに中からシーラントがあふれてくる可能性があるので、応急処置としてチューブを入れてクリンチャー化し、ひとまず帰宅するのも手です。
チューブラータイヤがパンクしたら
昔はチューブラータイヤーがパンクしたら自分でタイヤを縫って復元するサイクリストもいましたが、基本的にはタイヤの張替えになります。市場での流通量が年々減少しており、タイヤの価格が高騰化しているのでクリンチャーよりも費用がかかります。チューブだけを持ち歩いてパンク修理することができないため、パンクに備えてチューブラータイヤを常に携帯する必要があります。
まとめ
以上が、サイクリスト必須スキルの「パンク修理」の紹介です。初挑戦の方は、いざ実践する前に自宅で何度か練習してみてください。いざその時になると頭が真っ白に…という体験談を耳にしたことがあるので、もしもの際に備えて流れを把握しておきましょう。
パンク修理ができるとサイクリングの安心感がぐっと高まります。より長い距離を走れるようになりますね。ぜひRoute Shareで次のサイクリング計画を立ててみてはいかがでしょうか。
公式SNSで情報を発信中
RouteShareの使い方、旅行情報・テクニックなど楽しく旅行ができるノウハウを紹介しています。ぜひフォローしてください。
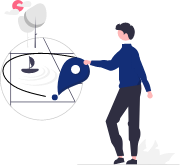
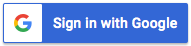
Googleアカウント、メールアドレスで無料ですぐに始められます。
登録後にStravaを連携することでアクティビティからすぐに
ルートをインポートすることも可能です。

