
投稿日:2024/11/14
更新日: 2024/11/17
間違いやすい交通ルール20選!車の運転などでうっかり違反を無くして、ドライブを楽しもう!
ドライブを楽しむためには、安全運転が不可欠です。
しかし、交通ルールの中には誤解しやすいものやつい見落としてしまいがちなものも少なくありません。
この記事では、特に自動車、自転車、向けに勘違いされやすい or 最近改正された交通ルールを7項目紹介します。違反を未然に防ぎ、安全で快適な移動を心掛けましょう。
「自動車向け」の間違いやすい交通ルール

一般道でも後部座席はシートベルトは必須!

高速道路だけ全席シートベルトは必須!と勘違いして、一般道での後部座席は絞めなくても大丈夫...!!
なんて考えている方もいるのではないでしょうか?
実は、道路交通法の改正により、2008年6月1日から全席でシートベルトの着用が義務化されました。
運転席や助手席だけでなく、後部座席でもシートベルトを着用していない場合は「座席ベルト装着義務違反」となり、違反点数が付きます。
運転者の責任となるため、乗車する際は忘れずに締めましょう。
※運転者の着用義務(道路交通法第71条の3第1項)
高速道路でインターを通り過ぎた時の対処

高速道路で降りる予定だったインターを通り過ぎた場合、諦めて次のインターで降りて多くの通行料を支払っていませんか?
「逆走・後退は厳禁!」は既にご存じかと思いますが、降りる予定だったインターを通り過ぎた場合は、焦らずに次のインターまで進み、一般レーンでその旨を申し出ることで料金所スタッフが目的のインターチェンジへ向かうように案内してくれます。
高速道路では、80km~100kmほどのスピードで走行しているため、間違った時に焦ってしまい交通事故を招きかねないですが、上記のことを知っていれば問題なさそうですね!
サンダル・ハイヒールでの運転はNG
「ちょっとスーパーマーケットに行くから」「地元で道は知っているから」といった理由で、サンダルやハイヒールで運転をしてしまったりしていませんか?
サンダルやハイヒールを履いて運転することは、運転に支障を及ぼすおそれがあるため、交通の教則では禁止されています滑りやすく、急ブレーキが難しくなる場合もありますので、運転しやすい服装や履き物などで運転するように心がけましょう。
靴下や裸足はOKなのか?
裸足や靴下であれば、フロアマットに引っかかったり操作が不安定になったりすることはありません。そのため、裸足や靴下であれば運転操作に支障はないと考える方もいるでしょう。
また、道路交通法では、靴下や裸足で運転することについて罰則規定が定められていないため、違反にはなりません。
しかし、裸足や靴下の場合、踏み込んだ力がペダルに適切に伝わらなかったり、足の指に踏力が集中してしまい想像通りの操作ができなかったりする可能性があります。また、万が一事故が発生した際に、クルマの部品が足に刺さってしまうことも考えられます。
そのため、裸足や靴下は運転操作という点だけを考えれば問題ないといえますが、適切な操作ができるかどうかという点で考えると最適ではないといえるでしょう。
よって、履き物を履いて運転することを推奨します。
※道路交通法第70条では「安全運転の義務」
「自転車向け」の間違いやすい交通ルール

夜間はライトを点灯(点滅はNG)

自転車はスピードも20km/h以下の場合が多く、一般的に自転車は近所や通い慣れた場所での運転が多いと思います。そんな慣れた環境下でライトを点灯せずに運転していることなんて...
この自転車の夜間走行では、ライトの点灯が必須です。点滅モードはNGなのでしっかり確認をしましょう。
また、日中でもトンネル内や濃霧などの暗い場所では、灯火をつける必要があります(道路交通法施行令第19条)。
※道路交通法52条1項
ヘルメットを着用(努力義務化)

自転車事故で頭部を損傷する割合は、死者の場合で5割以上を占めています。また、損傷者数も最も多く、死に至る可能性も高い部位です。
そんな中、交通事故の被害を軽減することを目的として、自転車に乗る際のヘルメットの着用は、2023年4月1日から年齢を問わずすべての自転車利用者に努力義務化されました。
ヘルメットの着用が義務化されつつあり、万が一の事故でも頭部を守るために重要ですね。
※道路交通法 第63条の11
自転車も車道走行が原則
実は自転車は道路交通法では自転車を軽車両と位置付けており、歩道と車道の区別がある場合は車道を通行するのが原則です。
軽車両とは
軽車両とは、原動機を持たず、レールを使わずに走行する車両を指します。具体的には下記です。
- 自転車、荷車、その他人もしくは動物の力(原動機を持たない車両のこと)により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)
- 身体障害者用の車いす、歩行補助車や小児用の車以外のもの
※道路交通法の第2条第11項
よって、自転車は歩道ではなく、車道の左側通行が原則です。
自転車が歩道を通行することができる場合
- 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
- 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合。
- 著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など。
そういった状況下では例外として認められていますが、走行時は歩行者を優先し、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
並走は禁止

お友達や家族と一緒に自転車走行している時に、会話をするために並走して運転していませんか?
前述していますが、自転車は軽車両に分類されていますので、並走は原則禁止です。自動車が車道で並走しない理由を一緒と考えていいでしょう。
並列での走行は事故の原因となるため避けるべき行為ですね。
※道路交通法第19条
まとめ
今回は、交通ルールの中でも「運転手が誤解のもと行ってしまいがち」「最近改正されたルール」を元に厳選して紹介しました。
道路交通法は、制定以降27回改正されており、昭和期に12回、平成時代に13回、令和時代に2回改正されています。制定当初は本則が124条でしたが、現在は309条にまでなっています。当記事も2024年11月現在の最新情報を元に作成しておりますので、運転する際は必ず最新の交通ルールに従って運転をしましょう。
自身の行動が他の道路利用者の安全にも影響を与えることを認識し、周囲と協力して交通ルールを徹底して守ることが大切です。
ドライブや移動をより楽しむために、交通ルールを今一度確認し、意識的に取り組んでいきましょう!
公式SNSで情報を発信中
RouteShareの使い方、旅行情報・テクニックなど楽しく旅行ができるノウハウを紹介しています。ぜひフォローしてください。
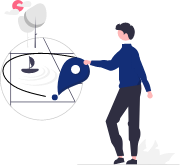
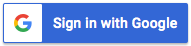
Googleアカウント、メールアドレスで無料ですぐに始められます。
登録後にStravaを連携することでアクティビティからすぐに
ルートをインポートすることも可能です。

